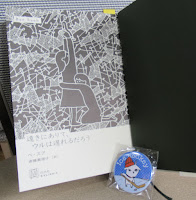ようやく時間ができたので、レベッカ・L・ウォルコウィッツ著『生まれつき翻訳』(監訳・佐藤元状、吉田恭子/訳・田尻芳樹、秦邦生、松籟社, 2021)を読みはじめる。監訳者の方々は「クッツェーファンクラブ」の面々なので、読むのを楽しみにしていたのだ。
まずは序章「世界文学の今をめぐって」をざっくり読んでいくと、クッツェーという作家名がかなり出てくる。そこはゆっくり読む。するとチカチカと点滅する文字群に出くわした。p24の3つ目の段落はこう始まる
「ニューヨークやロンドンなど出版業界の中心から外れた場所にいる英語作家も、翻訳を余儀なくされることがある。ケニアの作家グギ・ワ・ジオンゴが最初の一連の長編をキクユ語で出版することにしたのはよく知られているが、自らの翻訳で英語でも出版してきた。チヌア・アチェベの『崩れゆく絆』にはイボの言葉がそこここに使われているが、一九六二年、ロンドンのハイネマンの叢書で出版されたときには用語集が必要だったし、クッツェーの『石の女』は一九七七年に南アフリカで初版が出たが、英国版では一部がアフリカーンス語から英語に翻訳されている」(下線引用者)
アフリカ系/発の作家たちと言語との関係をざっと見渡す部分だが、下線を引いた箇所で「?」となった。クッツェーの第二作目に当たるこの本はまず、イギリスとアメリカで出たはずだ。念のため原文も当たってみたが、原文通りの訳になっているから、これは著者レベッカ・L・ウォルコウィッツの勘違いなんだろう。まず下線部前半。
1)クッツェーの『石の女』は一九七七年に南アフリカで初版が出たが
In the Heart of the Country(わたしはいくつかの理由で原タイトル通りに『その国の奥で』とする) の「初版は」たしかに1977年に出ているが、南アフリカのRavan社からではなくイギリスのSecker社からだ。同年にアメリカのHarper社からもタイトルが一語異なる形で出ている(理由は後述する)。南アフリカで英語とアフリカーンス語の混じった「バイリンガル版」として出たのは翌年の1978年2月*だ。出版にいたる事情は非常に複雑。この出版年の微妙なずれについては、2014年の拙者訳『サマータイム、青年時代、少年時代』(インスクリプト)の年譜にも、昨年の『J・M・クッツェーと真実』(白水社)の年譜にも載せた。だからここはちょっと残念。
クッツェーがこの作品を書き上げたときは2つのバージョンがあった、とカンネメイヤーの『伝記』(伝記 p288~)やデレク・アトリッジの著書(Attridge p22)は伝えている。デイヴィッド・アトウェルの作品論(p65~)にも詳しい。(参考図書はブログ下に)
 |
| Ravan 1978 |
2つのバージョンのうち1つはすべて英語のバージョン。もう1つは会話部分がアフリカーンス語のバージョンだ。ロンドンのエージェント宛てのクッツェーの手紙によると、会話部分にフォークナーが南部訛りの英語を用いたように、自分も英語でローカルな感じを出したいとやってみたがうまくいかなかった、とある。会話は英訳前のアフリカーンス語バージョンがしっくりくるとクッツェーは述べる。
テクストが海外版と南ア版で異なるこの作品の出版が、南アフリカで一年遅れた理由は、1970年半ばに南アフリカの検閲制度が大きく変化し、作家や編集者が検閲委員会の動きを注視せざるをえなくなったことと関連があるようだ。さらに、旧植民地をも市場にしたいイギリスの出版社と南アフリカの極小出版社との、販売権をめぐる複雑な事情が絡んでいる。
これはまだ初作『ダスクランズ』が南アフリカでしか出版されていなかったころで、クッツェーは二作目はイギリスやアメリカで出版したいと強く希望していた。そこでレイバンの編集者とイギリスのエージェントと同時に交渉していたらしい。その結果、まず英語のみのバージョンがイギリスとアメリカで出版され、会話部分がアフリカーンス語のバイリンガル版が翌年、南アフリカで出版ということになった。
 |
| Harper Collins 1977 |
米国版は内容は英国版と同じだが、タイトルが
From the Heart of the Country になった。これは、Harper の編集者から、
In the Heart of the Heart of the Country という書籍がすでにあって図書館に所蔵するときコンピュータ上混乱するので、
Here in the Heart of the Country にしてはどうかと提案されたクッツェーが、それでは長すぎるし、自分がつけたタイトルは
テキスト全体を貫くあるリズムを示しているのだ、として
From the Heart of the Country を提案し、決まった。(下線筆者)
クッツェーが2つのテクストを準備した理由は、農場を舞台にした会話場面の多いこの作品の本質と関わってくる。南アフリカの農場で用いられる言語は、『少年時代』を読むとわかるが、圧倒的にアフリカーンス語だ。会話はアフリカーンス語であるほうが、クッツェーを含む南アの読者にとって自然なのだ。次に下線の後半部分。
2)英国版では一部がアフリカーンス語から英語に翻訳されている。 |
| Secker&Warburg 1977 |
先行する「初版が」が事実と異なるので、理解しにくいのだけれど、ウォルコウィッツは「南アフリカの初版」をアフリカーンス語含みのバイリンガル版と考えたのだろう。 何語から何語への翻訳かは、アトウェルの草稿研究が明らかにしている。会話部分は最初アフリカーンス語で書かれていたが、作家が改稿の見直しをするとき、草稿の反対ページにアフリカーンス語会話の英訳を書きこむようになったのだ。「自分の作品は英語という言語にルーツをもっていない」と明言するにいたった作家の心情が、非常によく出ているのがこの農場を舞台にした『その国の奥で』だった。
というわけで、どうやらこの作品の出版年をめぐるウォルコウィッツの誤記に、「クッツェーファンクラブ」の面々は残念ながら気がつかなかったらしい。些細な誤記ではあるが、1970年代南アフリカの出版事情は、J・M・クッツェーという作家の誕生にとって重要なポイントなのだが。
なんでこんな文章を書いているのか、と自問してみる。どうやらそこには、日本のクッツェー研究者に南アフリカのことをもう少し突っ込んで探って欲しいと思っている自分がいることに気づく。アフリカなんか、と思わずに。クッツェーが生まれて育って、20代の10年間をのぞいて62歳まで暮らした土地なんだから。
ウォルコウィッツのこの本は、トピカルなテーマを追いかける文芸ジャーナリスト顔負けの奇抜な見立てと文章力で読ませてしまうところが、すごい。でもその足場として透かし見える軸は、「世界文学」としての英語圏文学をマッピングして描こうとする「北の英語文学理論」の欲望にあるのではないか。バッサバッサと斬新なテーマで切っていく勢いには、辺境で生み出される個々の作品の、いってみれば英語以外の「その他の言語」で書かれる作品の出版事情なんかにいちいちこだわらなくてもいい、という姿勢が見え隠れする。いや、ぜんぜん隠れてないか(笑)。村上春樹とJ・M・クッツェーを「翻訳」というキーワードでおなじ土俵に並べてしまうのだから。この2人にとって作家として生きる言語環境と、「翻訳」の切実性や必然性の依って立つところは、まるで異なるだろうに。
また born translated をわたしは「翻訳されて生まれてきた」と訳すことにしているが、それは「生まれつき翻訳」は「分類」「仕分け」には便利だが、作品が立ちあがる動きを切り捨てるニュアンスがあるためだ。おそらくそれは作品翻訳者の姿勢と、数多くの作品を「研究」する者の姿勢の違いからくると思われる。もう一つ、あえていうなら「生まれつき」に続く語にマイナスイメージ(差別語)を呼ぶ気配が消えないからだ。そのような表現を長く、耳から浴びつづけた世代だからかもしれないけれど。
翻訳はさぞや大変だっただろうなあと推察する。膨大な作品数と原註、そのファクトチェックの結果と思しき訳註で、クッツェーの書評集と小説の冊数をめぐる警告が入っていたりして、苦労の跡がしのばれます……ご苦労様でした。👏👏👏👏
ちなみに、2022.4.18現在のWikipedia(英語版)In the Heart of the Countryは、出版年、バージョンともに、きちんと事実を伝えています。💖
----
追記:2022.4.24──
1)参考図書をあげておきます。(『J・M・クッツェーと真実』にも入れました。)
・Derek Attridge: J. M. Coetzee and the Ethics of Reading, University of Chicago Press, Chicago, London 2004.
・Peter D. McDonald: The Literature Police, Oxford University Press, 2009.
・J. C. Kannemeyer: J. M. Coetzee, A Life in Writing, Scribe, 2012.
・David Attwell: J. M. Coetzee and the Life of Writing, Viking, 2015.
・Marc Farrant, Kai Easton and Hermann Wittenberg: J. M. Coetzee and the Archive: Fiction, Theory, and Autobiography, Bloomsbury, 2021.
・Robert Pippin: Metaphysical Exile on J. M. Coetzee’s Jesus Fictions, Oxford University Press, 2021.
2)『その国の奥で』のことは『J・M・クッツェーと真実』第三章「発禁をまぬがれた小説」で、部分訳も引用しながら、詳述しました。
-----
さらに追記:2022.11.12──
*「6月」と書きましたが、正しくは「2月」でしたので、訂正しました。
 とりわけジョン・クッツェーの生きた時代とぴたりと重なるアパルトヘイト時代の政治制度の内実や、人種による微妙な人間関係の心理をめぐる細部は、どんどん大雑把にまとめられて歴史の彼方へ葬り去られていくようだ。翻訳者も解説者も編集者も校閲者も、勘違いや見落としを最初から疑って、歴史的事実を正確に伝えるよう努力しなければいけない時代になった。
とりわけジョン・クッツェーの生きた時代とぴたりと重なるアパルトヘイト時代の政治制度の内実や、人種による微妙な人間関係の心理をめぐる細部は、どんどん大雑把にまとめられて歴史の彼方へ葬り去られていくようだ。翻訳者も解説者も編集者も校閲者も、勘違いや見落としを最初から疑って、歴史的事実を正確に伝えるよう努力しなければいけない時代になった。