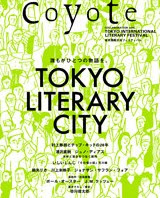今週は月曜、火曜とあわただしく札幌まで行ってきました。そのため日曜日の新聞に掲載された記事について、ここにアップする余裕がなく、あれよあれよと今日になりました。
あらためてご紹介します。
2013年5月26日(日曜日)朝日新聞読書欄「ニュースの本棚」に載った、福島富士男さんの「アフリカ文学は闘う」です。
先ごろ他界したナイジェリアのチヌア・アチェベから始まり、西アフリカ出身のオラウダ・イクイアーノの古典、『やし酒飲み』で日本でもおなじみのエイモス・チュツオーラ(彼は鍛冶屋兼作家という、大変ユニークな語り部的存在だった)、ケニアの巨匠グギ・ワ・ジオンゴ、コートジボワールのアマドゥ・クルマと続いて、最後にチママンダ・ンゴズィ・アディーチェが紹介されています。
代表作の『半分のぼった黄色い太陽』ばかりか、新作『アメリカーナー』まで論じられていています。アフリカ文学好きの方は必読!
紙面上部には書籍が三冊、写真とクレジット入りで紹介されているのですが、それが切れてしまいました。ごめんなさい!
あらためてご紹介します。
2013年5月26日(日曜日)朝日新聞読書欄「ニュースの本棚」に載った、福島富士男さんの「アフリカ文学は闘う」です。
先ごろ他界したナイジェリアのチヌア・アチェベから始まり、西アフリカ出身のオラウダ・イクイアーノの古典、『やし酒飲み』で日本でもおなじみのエイモス・チュツオーラ(彼は鍛冶屋兼作家という、大変ユニークな語り部的存在だった)、ケニアの巨匠グギ・ワ・ジオンゴ、コートジボワールのアマドゥ・クルマと続いて、最後にチママンダ・ンゴズィ・アディーチェが紹介されています。
代表作の『半分のぼった黄色い太陽』ばかりか、新作『アメリカーナー』まで論じられていています。アフリカ文学好きの方は必読!
紙面上部には書籍が三冊、写真とクレジット入りで紹介されているのですが、それが切れてしまいました。ごめんなさい!