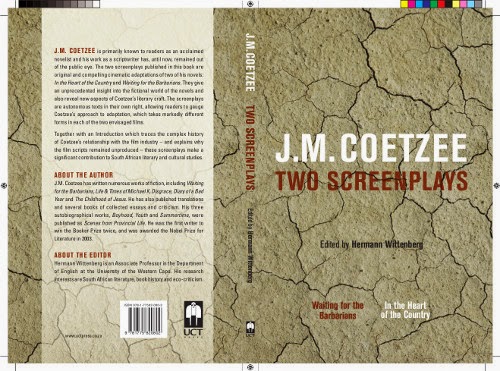ぶりかえした暑さも昨夜の雨でどこかへ。本格的に、秋の気配が近づいてきた。虫の音も冷たい空気のなかで澄んだ音色を響かせている。
 力を出し切ったクッツェー三部作、オースターとの往復書簡集、イベントなども終わり、本格的にチママンダ・ンゴズィ・アディーチェの『アメリカーナ』に取り組まなければならないときがやってきた。すでにかなりの量は訳してあるのだけれど、ここへきてぐんぐん進む。毎日進む。
力を出し切ったクッツェー三部作、オースターとの往復書簡集、イベントなども終わり、本格的にチママンダ・ンゴズィ・アディーチェの『アメリカーナ』に取り組まなければならないときがやってきた。すでにかなりの量は訳してあるのだけれど、ここへきてぐんぐん進む。毎日進む。 春先に枯れ枝を根元から刈り取っても、またしっかり生えてくる萩。今年も赤紫のグラデーションの美しい小花をたくさんつけて、風にゆられている。
春先に枯れ枝を根元から刈り取っても、またしっかり生えてくる萩。今年も赤紫のグラデーションの美しい小花をたくさんつけて、風にゆられている。西アフリカの大都市で育った女性が、アメリカに渡って体験するさまざまな大波、小波。移民労働の世界。肌の色の違い、髪の毛の縮れぐあい。それが決定的な要素となることの意味。物語はナイジェリアという土地を超えて、アメリカの境界も飛び越えて、いまやわたしたちの住む社会にもとどけられる。
そこには「アフリカ文学」という従来の枠には収まり切らない、若い書き手の作品があるのだ。そのこととアフリカの現実を切り離して考えていいということでは決してないのだけれど、それも、これも、また、現在のこの地球に住み暮らしている人間たちの、深くて複雑な内実なのだというしかないのだろう。心して訳していきたい。このとびきりの面白さを、早く読者と分かち合いたい。