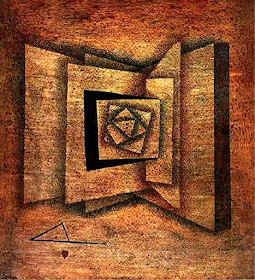先週末に駒場で面白い研究会があった。そこで、J・M・クッツェーの作品研究をしている院生の発表を聴いた。若い研究者たちの熱のこもった発表がとても面白かった。
 |
| 南アフリカ大使館fbから拝借 |
現在、クッツェー研究の世界的な潮流として、オースティンのクッツェー・アーカイヴの調査は不可欠だ。そこにおさめられた作家の創作ノート類を細かく調べることで、作品の立ちあがる瞬間、逡巡しながら作品を書き進むようす、それまでの草稿を反古にしてあらたな作品を書き出したきっかけなどが、細かく分かるようになったからだ。
各作品の立ちあがりと時代との絡みは、もちろん、じつに興味深いものがあるし、クッツェー作品にくりかえしあらわれる共通のモチーフやテーマで作品群を分析すると、思わぬ視界が開けそうな気配も強く感じられる。これからは各作品が、J・M・クッツェーの生い立ちや時代背景、彼の人生そのものと関連づけられながら、各作品のテーマとどう結びついているかを論じることで、この作家の全体像がクリアに見えてくることだろう。クッツェーが自分のペーパー類を生前に公開した、というのは、そのような研究姿勢を(つまり、作品の読み方を)作家自身が求めていると考えてまちがいない。
 |
| 筆者撮影、2011 |
その研究会のなかで、いやその後のオフ会だったか、ある人がふと口にしたことばが、ずっと頭から離れなかった。それは「クッツェーって風景をあまり描きませんね」ということばだ。それに対して「『マイケル・K』にはかなりありますが」とわたしは答えたけれど、その人が言った「風景描写」とわたしが言うものとはずれがあったように思う。
『マイケル・K』は一種のロードノベルだ。旅する主人公の目がとらえる個々の、地を這うような場面描写は、風景というよりはあくまで光景というか情景というか、そういうたぐいのもので、「風景/ランドスケープ」となると、もう少しスカーンと広い範囲の見晴らしのいいものだろうな、と思う。
そのことをここ数日、考えるともなく考えてきて、ふと思い至ったのは、そうか、南アフリカの白人作家や詩人は長いあいだ、まさに、この風景/ランドスケープを描いてきたのだ、ということだった。(公式の歴史文書は長いあいだ、19世紀のキリスト教到来の時代まで、われわれが現在南アフリカと呼んでいる内陸がいかに無人であったかという物語を伝えてきた──『ホワイト・ライティング』)
クッツェーは1989年に発表した『ホワイト・ライティング』のなかで、このブログでも何度もとりあげてきたが、誰もいない風景の美しさをことほぐ詩や小説について、ある批判を込めて書いた。つまり、美しいカルー、愛するカルー、誰もいない風景と、そこに多くはないにしろ人が住んでいたにもかかわらず、その人たちは滅びたものとして作品を書いてきた伝統がホワイトライティングにはあったのだ。
 |
| 筆者撮影:南ア出身のAttwell, Wittenbergと |
だから、その延長で南アフリカのランドスケープをことほぐことをクッツェーはみずからに禁じたにちがいない。白人である彼がこの土地の美しさを無条件に、手放しで書くことは、その土地を精神的に所有することにつながるからだ。本来ヨーロッパ人のものではなかった土地を「愛する」と言ってしまうことを抑制する心情がクッツェーには働いたのではないのか。
クッツェーという作家が抱く南アフリカという土地への屈折した意識/愛については、『サマータイム、青年時代、少年時代』の解説にも書いたけれど、あの土地をたんに自然/ランドスケープとして描くことに抵抗を感じ、抑制した意識がはたらいたことと、彼の作品内に風景描写が少ないこととは、密接な関係があると思うのだが、どうだろう。
これは私自身が北海道という土地の美しさを無条件に書くわけにはいかない、と感じることにも繋がっていくのだけれど。