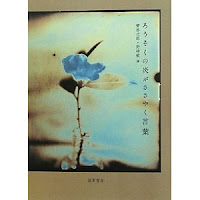「トンネルを抜けると、雪国じゃなくて、カルーですね」
 そんな冗談をいいながらガイドの F さんが運転する車で、制限時速130キロの国道一号線をおよそ100キロのスピードで走ったのは、内陸の町ヴスターをめざした日だ。「ユグノートンネル」というその長い、長いトンネルを通過すると、風景が一変した。
そんな冗談をいいながらガイドの F さんが運転する車で、制限時速130キロの国道一号線をおよそ100キロのスピードで走ったのは、内陸の町ヴスターをめざした日だ。「ユグノートンネル」というその長い、長いトンネルを通過すると、風景が一変した。
まっすぐ走る道路の両側は、赤っぽい土のうえにしがみつくようにして生える低木、ブッシュがはてしなくつづく。灌木がならぶ平地に一列にならんでいるのは防風林だ。背の高い緑の木々はもともと南アフリカにはなかったもので、すべて、植民者がヨーロッパやほかの大陸からもってきて植え付けたものだという。ユーカリ、オーク、ポプラ、ジャカランダといった高木が農場の周辺に植林されている。貯水池も見える。
『マイケル・K』ではステレンボッシュで母親をなくした主人公がプリンス・アルバートへ向かう道中、球技場のそばの空き家で一夜をあかし、翌日どしゃぶりの雨のなかで畑からじかに生の人参を食べる場面があった。球技場と道路を隔てるようにしてユーカリが一列植わっていたことを思い出した。
土埃の町だと『少年時代』でジョン少年が呼んだヴスター。駅前の広場につづく通りには写真のようにユーカリの並木道があったけれど、春先の強い陽射しに人気もなく、どこか打ち捨てられた感じの、荒涼とした風景が広がっていた。
ケープタウンのウォーターフロント近くだったろうか、鉄道がはじめて敷かれたことをしめす場所があった。そばに防火林が植わっていた。乾燥したケープでは、列車の車輪とレールの軋轢による火花で頻繁に火事が起きた。それで植民者たちは防火林を植えて、火花が飛び散っても緑の葉にあたって、鎮火するようにしたのだという。
 下の写真はケープタウンへの帰路、トンネルではなく山越えをしたときの峠の休憩地、デュ・トイ渓谷からのながめ。ここでふたたび風景は一変して、海にむかって緑の平地や葡萄園がつづくようになった。
下の写真はケープタウンへの帰路、トンネルではなく山越えをしたときの峠の休憩地、デュ・トイ渓谷からのながめ。ここでふたたび風景は一変して、海にむかって緑の平地や葡萄園がつづくようになった。
1988年にクッツェー作品を初めて読んで以来の、念願のケープタウン旅行は、2011年をふりかえったとき、数少ない、実りの多い「良い」出来事だった──了。
付記:今日のつづきの来年は少しでも「良い」年になるように、祈るだけでなく、動きたい──大晦日に。
 そんな冗談をいいながらガイドの F さんが運転する車で、制限時速130キロの国道一号線をおよそ100キロのスピードで走ったのは、内陸の町ヴスターをめざした日だ。「ユグノートンネル」というその長い、長いトンネルを通過すると、風景が一変した。
そんな冗談をいいながらガイドの F さんが運転する車で、制限時速130キロの国道一号線をおよそ100キロのスピードで走ったのは、内陸の町ヴスターをめざした日だ。「ユグノートンネル」というその長い、長いトンネルを通過すると、風景が一変した。まっすぐ走る道路の両側は、赤っぽい土のうえにしがみつくようにして生える低木、ブッシュがはてしなくつづく。灌木がならぶ平地に一列にならんでいるのは防風林だ。背の高い緑の木々はもともと南アフリカにはなかったもので、すべて、植民者がヨーロッパやほかの大陸からもってきて植え付けたものだという。ユーカリ、オーク、ポプラ、ジャカランダといった高木が農場の周辺に植林されている。貯水池も見える。
『マイケル・K』ではステレンボッシュで母親をなくした主人公がプリンス・アルバートへ向かう道中、球技場のそばの空き家で一夜をあかし、翌日どしゃぶりの雨のなかで畑からじかに生の人参を食べる場面があった。球技場と道路を隔てるようにしてユーカリが一列植わっていたことを思い出した。
土埃の町だと『少年時代』でジョン少年が呼んだヴスター。駅前の広場につづく通りには写真のようにユーカリの並木道があったけれど、春先の強い陽射しに人気もなく、どこか打ち捨てられた感じの、荒涼とした風景が広がっていた。
ケープタウンのウォーターフロント近くだったろうか、鉄道がはじめて敷かれたことをしめす場所があった。そばに防火林が植わっていた。乾燥したケープでは、列車の車輪とレールの軋轢による火花で頻繁に火事が起きた。それで植民者たちは防火林を植えて、火花が飛び散っても緑の葉にあたって、鎮火するようにしたのだという。
 下の写真はケープタウンへの帰路、トンネルではなく山越えをしたときの峠の休憩地、デュ・トイ渓谷からのながめ。ここでふたたび風景は一変して、海にむかって緑の平地や葡萄園がつづくようになった。
下の写真はケープタウンへの帰路、トンネルではなく山越えをしたときの峠の休憩地、デュ・トイ渓谷からのながめ。ここでふたたび風景は一変して、海にむかって緑の平地や葡萄園がつづくようになった。1988年にクッツェー作品を初めて読んで以来の、念願のケープタウン旅行は、2011年をふりかえったとき、数少ない、実りの多い「良い」出来事だった──了。
付記:今日のつづきの来年は少しでも「良い」年になるように、祈るだけでなく、動きたい──大晦日に。